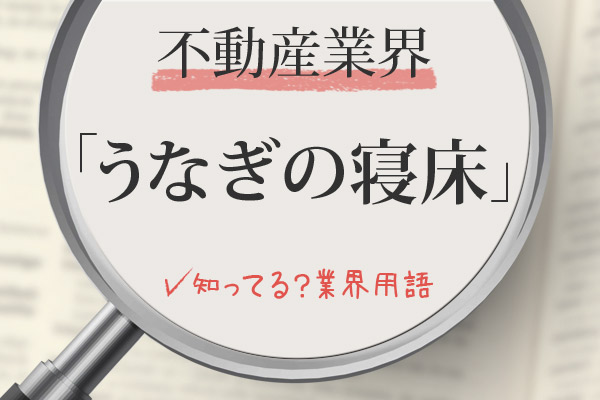不動産では従業員の間で、「うなぎの寝床」という言葉が使われているといいます。この言葉からは、「うなぎが寝る場所は川の中」というものが思い浮かんできますが、実はある間取りをさす言葉として使われています。
カウンター式の飲食店に多い「うなぎの寝床」
まず引っ越しを考えるとき、間取りや家賃、立地を重視するのではないでしょうか。その中でも間取りを選ぶときは、日当たりの良さや部屋数、収納スペース、トイレとお風呂が別なのかという点を意識するでしょう。
もしかしたら、不動産で見かける間取りの中には、「うなぎの寝床」のような物件があるかもしれません。
この「うなぎの寝床」とは、間口が狭く、奥行きがある細長い間取りの部屋をさします。岩の隙間など狭く細い場所を好むうなぎの巣の形状と似ていることが、語源といわれています。
具体的にどのような間取りなのかというと、寿司屋によく見られるカウンターと壁の幅が狭い間取りです。そのほかにも、古い家屋にも多く見られます。
一見、風通りや採光が悪い印象のあるうなぎの寝床ですが、奥行きがあるので空間全体が広く見えることや、建築士の腕や隣地次第では良い物件になることもあります。
京都に多い、うなぎの寝床の理由
うなぎの寝床はある昔のシステムの影響で、京都に多くあったといわれています。それは江戸時代のころ、賦課金というシステムがあったからです。これは今でいう固定資産税のようなものをさします。
当時は間口の大きさによって決められており、その賦課金の負担を少しでも減らすために、うなぎの寝床のような、狭く奥行きのある家が多く建てられたのが始まりといわれています。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・カードローン・スマホローンのよくある7つの疑問(PR)
・「dジョブスマホワーク」で高ポイントをもらう方法
・「老後破産」しないために読みたい
・dポイントで投資できる?100ポイントからでOK!(外部)
・ポイ活特集