2024年1月から始まった「新NISA」は、昨年までのNISAと比べると、投資できる金額や投資商品を非課税で持てる期間(非課税保有期間)が大きく変わっていますが、特に変更した点について多くの人が勘違いしていたり、知らなかったりしているようです。
新NISAは旧NISAとは別の「新しいNISA制度」
新NISAは、旧NISAに変更が加えられたものではなく、新しく作られた別の制度であり、旧NISAとは似ているものの違っている点もあります。次の3つの点をおさえておきましょう。
おさえたい点1 新NISAは投資できる金額が増え、いつまでも非課税で持てる
昨年までのNISAと比べて、新NISAは投資できる金額が増え、投資商品をいつまでも非課税で持てるようになりました。
新NISAで投資できる金額の上限は1年あたり360万円まで、生涯で1800万円までです。この額までの投資なら、非課税で保有できます。つまり毎年360万円投資して、金融商品を売らなければ5年で枠がいっぱいになります。
また、昨年までの旧NISAには非課税保有期間が設けられていましたが、新NISAではその期間に制限がなくなり、一生涯、税金がかかることなく持ち続けられます。
上の例では、5年で枠いっぱいまで投資した商品を、ずっと非課税で持ち続けられるわけです。なおNISA口座で買った商品を売ると、その分、枠が復活します。
おさえたい点2 「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は、一般NISAとつみたてNISAを引き継いでいる
新NISAは旧NISAとは違うと説明しましたが、仕組みは似ています。というのも新NISAには「成長投資枠」と「つみたて投資枠」がありますが、それぞれ昨年までの一般NISA、つみたてNISAの役割を引き継いでいるのです。たとえば、新NISAの「つみたて投資枠」は、旧つみたてNISAのように、買える商品が金融庁が認めた長期保有に向いた投資信託などだけです(株は買えません)。
ただし、投資できる金額は、一般NISAとつみたてNISAと比べて大幅に増えています。
旧一般NISAは、年間120万円まで投資できました。非課税保有期間は最大5年なので、生涯で投資できる金額の合計は600万円でした。また、旧つみたてNISAは、年間40万円まで投資、非課税保有期間が最大20年なので、生涯で投資できる金額の合計は800万円でした。
それが新NISAでは、成長投資枠で年間の投資上限が240万円(旧一般NISAの2倍)、つみたて枠は1年で120万円です(旧つみたてNISAの3倍)。さらに、旧一般NISAと旧つみたてNISAは、どちらか一つを選ぶ必要がありましたが、新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠を同時に使えますので、合計で年間360万円(240万円+120万円)まで投資できます。
なお、新NISAの非課税保有限度額は1,800万円で、そのうち成長投資枠で使える金額は1,200万円までですが、つみたて投資枠には成長投資枠のような制限はありません。つみたて投資枠の年間の上限は120万円ですので、15年かけて積み立てれば、1,800万円全てをつみたて投資枠で使うこともできます。
成長投資枠で投資できる商品は、一般NISAとほぼ同じ、上場株式や投資信託などです。一方、つみたて投資枠で投資できる商品は、これまでのつみたてNISAと同じ、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託です。
おさえたい点3 新NISAはロールオーバーがなく、旧NISAからもできない
新NISAではロールオーバーがなくなり、旧NISAから新NISAへのロールオーバーもできません 。ロールオーバーとは、非課税保有期間が終わった際、持っている金融商品を、翌年の新たな非課税投資枠に移すことです。
これまでの旧一般NISAや2023年で終わったジュニアNISAではこのロールオーバーができましたが、新NISAは非課税保有期間が無期限となるため、そもそもロールオーバーをする必要がなくなったのです。また、旧NISAと新NISAは違う制度ですので、旧NISAの金融商品を新NISAに移すことはできません。
旧NISAで買った商品は、非課税保有期間が終わるタイミングで課税口座に移すか、または売るか、どちらか選ぶ必要があります。
NISAを始めるのに必要なのは、まずNISA口座を作ること
NISAは証券会社で専用のNISA口座を作る必要があります。NISAではない課税口座(特定口座、一般口座)を持っているだけでは始められません。
NISA口座は証券会社だけでなく銀行でも作れるが取扱商品数が異なる
NISA口座は、証券会社だけでなく銀行でも作れます。
それぞれの特徴としては、店舗型証券や銀行は店舗や窓口で直接相談ができますが、ネット証券と比べると手数料は高めです。ネット証券は窓口で直接話を聞くといったことはできませんが、ネット上で取引が完了し、手数料が安い傾向にあります。
また、店舗型証券や銀行では、「つみたて投資枠」対象ファンドを10〜20本程度しか取り扱いませんが、ネット証券では百数十本〜200本程度と、豊富に取り扱っています。
さらに、銀行では上場株式やETF(上場投資信託)の取り扱いがありませんので、これらの点に注意して口座を開く金融機関を決めましょう。なお、NISA口座は、1人につき1口座しか作れません。
2023年までに旧NISAを始め、既にNISA口座を持っている人は、その金融機関で自動的に新NISAの口座が作られます。 現在の金融機関でそのまま新NISAを始めるなら、口座を開くために自分で行う手続きはありません。
これまでの金融機関とは別の金融機関で新NISAの口座を持ちたい場合は、手続きを行えば新NISA口座を移せます。
ただし、変更の手続きができる期間は、金融機関を変えたい年の前年10月1日から、変更したい年の9月30日までです。
また、新NISAには、「買い付けができるのは年に1口座のみ」という原則がありますので、変更したい年に現在の金融機関で金融商品を買い付けてしまうと、その年は新しい金融機関では買えなくなるので注意が必要です。
口座開設はオンラインや郵送、窓口でできる
NISA口座を開くには、パソコンやスマホなどのオンラインのほか、郵送、窓口などで申し込みます。
これからNISA口座を作るなら、NISA口座の開設に必要なものや、作成の流れを確かめておきましょう。
ただし、各金融機関によって必要なものや口座開設の流れは多少異なりますので、口座を開きたい金融機関のウェブサイトなどで詳細を確かめてください。
NISA口座の開設に必要なもの・書類

1 金融機関ごとの口座開設申込書類
2 本人確認書類
(マイナンバーカードがある場合はマイナンバーカード1枚で可、ない場合はマイナンバー記載の住民票の写しか通知カード+運転免許証かパスポート等の本人確認書類)
3 取引印鑑
(金融機関の窓口で口座を開く場合)
申し込みの流れ
NISA口座申し込みの流れは以下の通りで、大まかに「必要な口座の開設・書類の提出・審査・NISA口座の開設」と進みます。
1 口座を開く……NISA口座以外にも所定の口座が必要
NISA口座を持つには、NISA口座のほかにも必要な口座を開く必要があります。銀行では普通預金口座と投資信託口座、証券会社では証券総合口座が必要です。
2 必要書類の提出……WebからアップロードでもOK
口座開設申込書類、本人確認書類などの必要書類は、郵送のほか、Web上で入力、またはアップロードで提出できます。
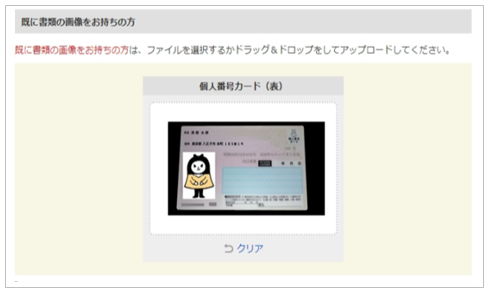
3 審査……税務署で重複口座がないか確かめる
提出された書類をもとに、金融機関は税務署でNISA口座の重複がないか確かめます。この確認には1~2週間程度かかります。
4 NISA口座の開設……一般的に1~3週間はかかる
NISA口座に重複がないことが確認されたら、NISA口座が開かれます。税務署への重複確認に少し時間がかかるため、申し込みから開設までには一般的に1~3週間程度かかります。
なお金融機関によっては、NISA口座を開設すると、現金のキャッシュバックやポイント還元が受けられる、投資信託の販売手数料が無料になるといったお得なキャンペーンを行っているところもあるので、そうした金融機関を探すとよいでしょう。
NISAにもデメリットや注意点はある
NISAは非課税でずっと投資できるメリットがある制度ですが、一方で、デメリットや注意点もあります。
注意点1 投資である以上、損をする可能性がある
新NISAも投資である以上、元本割れして損をする可能性もあります。買った商品が値下がりすることがあるからです。
たこのため、投資は長い期間にわたって続けることで、リスクを減らす努力が必要です。一般に、投資のリスクを減らすには、積立投資を基本にNISAを運用し、運用中に値下がりしても、投資をやめたり資産を売ったりせず運用を続けることが大切と言われています
注意点2 特定口座や一般口座との損益通算、損失の繰越控除ができない
NISA口座での損失は税務上ないものと見なされるため、特定口座や一般口座(NISA以外の課税口座)で持っている有価証券の売買益や配当金との損益通算ができません。
損益通算とは、投資の利益から損失を差し引くことです。損益通算ができる特定口座などであれば、利益が10万円出ても、損失が4万円出ていれば、税金がかかるのは10万円から4万円を差し引いた6万円にだけになります。
また、NISA口座では、損失の繰越控除もできません。 損失の繰越控除とは、その年の損失を控除しきれない時、翌年以降にその損失を繰り越して翌年以降の利益から控除できる制度です。
NISAは、利益が出た時は税金がかからないというメリットが受けられますが、損失が出た時は、損益通算や繰越控除ができないことでデメリットのほうが大きくなってしまいます。
注意点3 非課税の対象になるのはNISA口座で新たに買った金融商品のみ
NISAで非課税になるのは、NISA口座で新たに買った金融商品のみで、既に特定口座や一般口座で買った金融商品を、NISA口座に移して非課税で運用することはできません。
また、旧NISA口座の商品を新NISA口座に移したり、反対に新NISA口座の商品を旧NISA口座に移したりもできません。
旧NISAと新NISAは違う制度ですので、旧NISA口座で持っている商品を新NISAでも運用したい場合は、新NISA口座で新たに買い直す必要があります。
新NISAで毎月30万円、10万円、5万円積み立てた時の非課税メリットは?
新NISAは投資できる金額が大きく増えたことで、最大で月30万円積み立てられ、さらに、投資期間が長く持てることで、非課税メリットも大きくなります。
非課税保有限度額1,800万円を使い切るとして、毎月30万円積み立てるケース、毎月10万円積み立てるケース、毎月5万円積み立てるケースを比べると、お得になる税金にはどのくらい違いがあるのでしょうか。
毎月30万円を5年間積み立てると、約28万円分の税金がお得になる
月30万円は大きな金額ですが、定年を間近に控えていて、できるだけ早く資金を貯めたい人などにはおすすめのプランです。
毎月30万円ずつ積み立てると、非課税保有限度額を使い切るのに5年かかります(30万円×12ヵ月×5年=1,800万円)。
年3%で運用できた場合、NISAの非課税メリットによって税金がかかる場合より28万8,893円多く受け取れ、運用益は142万2,070円、元金と運用益の合計は1,942万2,070円になります。
毎月10万円を15年間積み立てると、約95万円分の税金がお得になる
40〜50代の人でもう少し多く積み立てられる場合は、月7〜10万円を目安にしましょう。
毎月10万円ずつ積み立てると仮定すると、非課税保有限度額を使い切るのに15年かかります(10万円×12ヵ月×15年=1,800万円)。
年3%で運用できた場合、税金がかかる場合より95万688円多く受け取れ、運用益は467万9,737円、元金と運用益の合計は2,267万9,737円になります。
毎月5万円を30年間積み立てると、約223万円分の税金がお得になる
若い世代は投資する時間が長く取れますので、毎月3万円や5万円など無理のない金額を長く積み立てていきましょう。
ここでは毎月5万円ずつ積み立てるとすると、非課税保有限度額を使い切るのに30年かかります(5万円×12ヵ月×30年=1,800万円)。
年3%で運用できた場合、税金がかかる場合より223万6,075円多く受け取れ、運用益は1,100万7,014円、元金と運用益の合計は2,900万7,014円になります。
いずれのケースも、運用益に税金はかかりません。また、これらのシミュレーションから分かる通り、同じ1,800万円を積み立てるにしても、長い時間をかけて投資したほうが非課税メリットや運用益が大きくなります。
新NISAはいつでも好きなタイミングで始められますが、投資期間が長いほうがお金を増やすのに有利な点を踏まえ、できるだけ早めに始めましょう。
新NISAのよくある勘違いや知られていない点
新NISAは旧NISAが拡充された制度ですが、旧NISAとは異なる点があり、まだ始まったばかりで知られていない点や勘違いも多いようです。新NISAの紛らわしい点は、今のうちによく理解しておきましょう。
Q1 「つみたて投資枠」ではなく「成長投資枠」で投資信託は買える?
A1 「つみたて投資枠」では投信しか買えないため、逆に「成長投資枠で買えるのは個別株のみ」と思われがちですが、「成長投資枠」では投資信託など、つみたて投資枠の対象商品も買えます。
また、新NISAの年間投資額は、成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円の合計360万円ですが、成長投資枠でも投資信託を積み立てられるため、360万円全額を積立投資に使うこともできます。
Q2 新NISAでは米国株式も買える?
A2 旧NISAでは、米国株式に対応していない金融機関もありましたが、新NISAでは成長投資枠の対象商品に米国株式が追加され、買うことができます。
なお新NISAの成長投資枠では、海外のETFやREITも買えます。ETFとは、金融商品取引所に上場している投資信託のことです。REITとは、多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルやマンションなど複数の不動産を買い、そこから得た賃貸収入や売買益を投資家に分配する商品で、投資信託の仲間です。
新NISAは、つみたて投資枠と成長投資枠が同時に使えますので、こうした幅広い商品に投資する機会があります。
Q3 非課税保有限度額1,800万円に達したら、もう投資できない?
A3 新NISAには、生涯に投資できる上限として1,800万円の非課税保有限度額がありますが、もしこの上限に達してしまっても、金融商品を売れば、売った分の投資枠が翌年以降に復活し、再利用できます。
ただし、非課税枠が復活するのは、あくまで「生涯の投資枠」です。商品を買った年と同じ年に商品を売ったとしても、年間の投資枠が空くわけではありませんので、注意しましょう。
Q4 利益が増えて1,800万円を超えたら税金がかかる?
A4 NISAでは、利益ではなく、金融商品を買った時の金額で非課税枠を管理しますので、利益が増えて1,800万円を超えたとしても、超えた分に対して税金がかかることはありません。
たとえば、毎月6万円を25年間積み立てると、投資元本は非課税枠の上限である1,800万円になり、年3%で運用できたとすると、25年後の資産総額は約2,667万円になります。非課税枠の上限1,800万円からは、約867万円増えますが、増えた分に税金はかかりません。
Q5 未成年もジュニアNISAの代わりに新NISAを使える?
A5 2023年までは、未成年向けのNISAである「ジュニアNISA」がありましたが、新NISAの場合、未成年の子供名義で新NISA投資はできません。新NISAは18歳以上の成人が対象の制度です。
この「18歳以上」とは、その年の1月1日時点での年齢が基準となります。2024年1月1日時点で17歳の人は、誕生日が来て18歳になっても2024年中の口座開設はできず、2025年1月1日以降に口座を開く必要があります。
早めに新NISAを始めよう
新NISAには、旧NISAとは異なる点も多くありますので、違いや仕組みについて、必要なポイントはしっかりおさえましょう。
新NISAはこれまでとは違って制度に期限がありませんので、資金計画に合わせていつでも好きな時にスタートできます。
ただし、お金を増やすには、投資期間を長く設けたほうが有利ですので、制度を理解したら早めに運用を始めましょう。
文・武藤貴子(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部