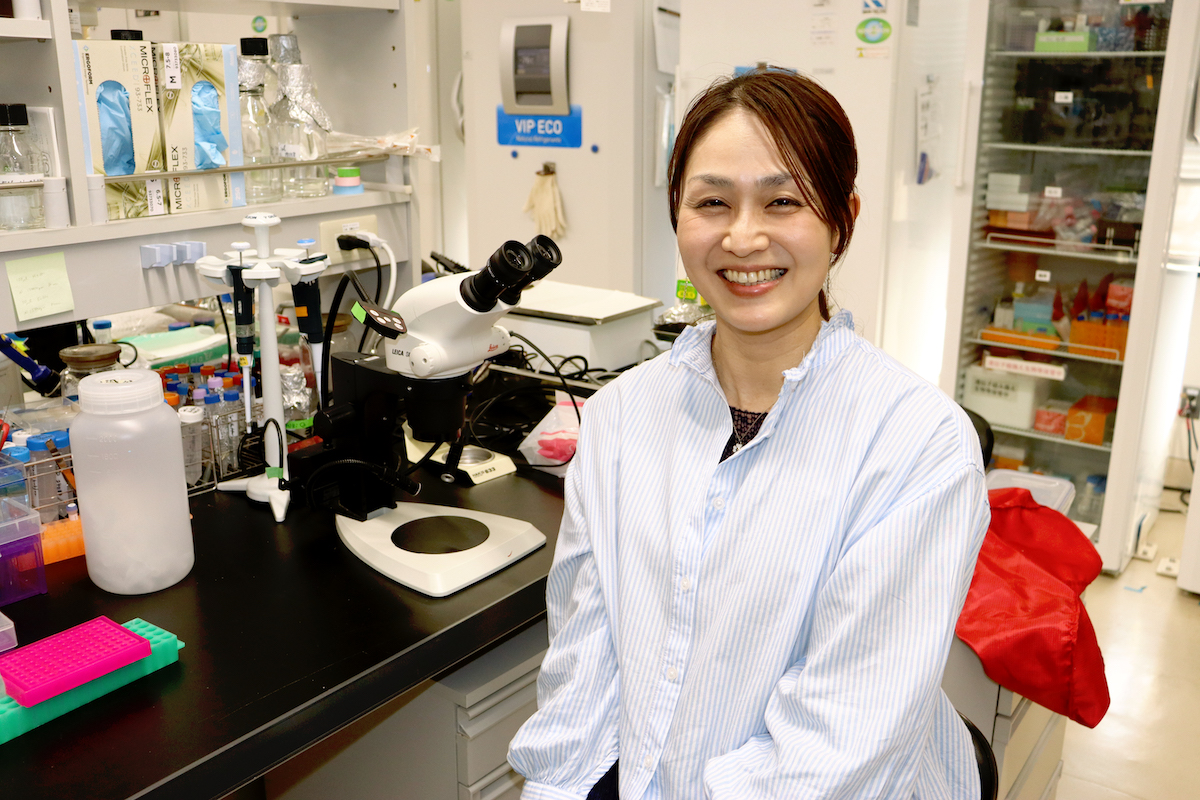
孤立したアリが、なぜ早死にするのかに迫った1冊の新書が発売となり、話題を集めている。国立研究開発法人産業技術総合研究所で、アリの社会性研究を進める古藤日子氏による『ぼっちのアリは死ぬ――昆虫研究の最前線』(ちくま新書)だ。
ミツバチやシロアリなどと同様、集団を作り社会的構造を備えながら分業を行って生活している社会性昆虫のアリ。本書は、孤立したアリの「すみっこ行動」の謎を、実際の写真や図解を差し込みながら紐解いていく。
2010年に東京大学大学院博士課程を終了後、2011年から13年までスイスのローザンヌ大学に留学し、“アリ”と出会った古藤氏。実は「予定していた研究テーマがうまくいかなくて」始めたテーマだったとか。それが今や「宝箱みたいな生き物です」と語る古藤氏に話を聞いた。
■細胞レベルでの社会的コミュニケーションに惹かれた学生時代
――「群れから離されたアリが死ぬ」こと自体は、80年も前から分かっていたんですね。
古藤日子(以下、古藤):本著でも触れていますが、80年以上も前の論文で発表されています。公園などで見かける普通のアリを連れてきて、研究室の箱の中で1匹、2匹、5匹、10匹と、いろんな単位で飼うと、1匹にしたアリはすぐに死ぬんです。アリだけでなく、社会性昆虫と言われる昆虫は実はみなそう。どの種でも1個体のほうが早く死にます。ただし80年前は「そういう発見をした」で終わり。そこで何が起こっているのかの研究は進んでいませんでした。
――そこで、古藤さんは「ぼっちになると、どうして死に至るのか」「何が起こっているのか」を研究したと。
古藤:そうです。当時は技術的にも研究が難しかったところもあったと思います。この本では、「なぜ死んだの?」ということを研究した最前線を紹介しています。
――大学院の博士課程修了後、スイスの大学に留学生として行かれたときに、このテーマに取り組み始めたとか。
古藤:学生時代に研究を始めたときにはショウジョウバエを使っていました。ショウジョウバエは、リソースセンターが世界各地にある主役級の「モデル生物」です。60日で一生が終わるので研究するのに最適ですし、遺伝学的な操作も簡単にできます。これを使って、細胞が生きる/死ぬの仕組みについて調べたのが、私の学生時代の研究の入り口でした。
――細胞が生きる/死ぬ。
古藤:隣り合う細胞同士は、お互いに隣にどんな細胞がいるかを意識して、コミュニケーションをしているんです。そこから「私は神経になりますよ」「私は皮膚になります」と運命が決まっていくのですが、その過程で失敗してしまった細胞は、自ら死んでいく選択をする。社会的なコミュニケーションが、私たちをかたち作る細胞レベルにもあって、そうして運命が決まっていくというのが面白くて、もっと掘り下げたいと思っていました。それで学生時代が終わり研究者としてキャリアを選択する際に、生物の「社会性」について、もっと研究してみたいと考えたんです。
■ピンチの中で出会った、二次元バーコードを使った“アリ”の研究
――ただ、スイスに渡られた最初の段階では、「ぼっちのアリ」の研究をする予定ではなかったそうですね。
古藤:はい。予定していた研究テーマがなかなかうまくいかなかったんです。そのため「2年間、留学生として派遣してもらっている間にもっと何かできないか」と。そこで最初の話に戻りますが、80年以上前に書かれた論文というのはフランス語のもので、当時フランス語が全く読めなかった私は読んでいませんでした。それを「こういう現象があるんだけど」と先生や同僚たちが見せてくれたんです。
――異国でのピンチの中で「ぼっちのアリ」に出会ったんですね。しかしアリの行動観察をしていくのは大変そうです。
古藤:フォローするのが相当キツイことは、想像していただけるかと思います。たとえば教室の中に10人保育園児がいたとして、その一人ひとりの行動をずっとフォローするって難しいですよね。
――難しいですね。
古藤:私がスイスに行ったときは、ちょうど二次元バーコードを使った行動解析が研究室で開発されていたところで、「これを使って研究を進めようぜ!」とみんなで息巻いていた時期でした。それで、低温で仮死状態にしたアリ1匹1匹の背中に二次元バーコードを貼り、回復して動き出したアリたちの行動をビデオで収めれば、それぞれどんな行動をしているのかが分かると。アリの研究自体が初めてでしたし、自分がやってみたいと思い描いてきた研究テーマはそのままではうまくいかないかもしれない、とネガティブな状況の中でのスタートでしたが、ほかの論文や多くの候補のテーマのなか「これをやってみよう」と思えるものに出会えた感覚がありました。
■宇宙飛行士の向井千秋さんの話を聞いて生物学にさらに興味を持った
――さかのぼって、先生の子ども時代についても教えてください。小さな頃から生物や研究には興味があったのでしょうか。
古藤:生物学への興味はありましたが、虫は好きではありませんでした(苦笑)。生物学や研究への大きな影響を受けたのは現在、東京理科大学で特任副学長をされている、日本人女性初の宇宙飛行士・向井千秋さんの存在です。私が小学生から中学生のときに、向井さんが2度宇宙飛行をされました。向井さんにはお医者さんというバックグランドがあって、宇宙で生物学的な実験をされているということと、女性であったこともあり、当時すごくニュースになっていました。
――よく覚えています。
古藤:向井さんは宇宙飛行士ですが、お話を聞いたり書物を読んでいて、生物への興味や生物学者への憧れが大きくなってきました。あとは、高校生ぐらいのときにNHKの『驚異の小宇宙 人体』という当時としては最先端のCGを使ったドキュメンタリー番組がありまして。こちらもすごく好きでよく見ていました。
――面白かったですね。
古藤:クローン羊のドリーが誕生したり、ES細胞(幹細胞)が出来たり。宇宙で生物実験をしたらどうなったとか、生物学において分からないことがたくさんあるのと同時に「そんなことできちゃったの?」というニュースが日常的にあった時代で、そういったところから興味を深めていきました。ただ、子どもの頃から「虫がすごく好きです!」といったタイプでは全然ないので、そういう意味で自分が異端だという気持ちはどこかにあります。
――そうなんですか?
古藤:ほかの多くの生態学や昆虫学の研究者さんたちとは、バックグラウンドが違うと感じることが時折あります。それでもコツコツ観察したり、積み上げていくことは好きでした。あと“見る”ということ。子ども時代には、証明するというところまではいきませんでしたが、「なんでこうなるんだろう」と観察することは、小さなころから地味に好きでしたし、結局それが今もとても大事だなと思っています。
――研究者はやっぱり「観察」が好きでないと務まりませんよね。
古藤:それとどこを見るか、ですね。たとえば同じ映画を2時間観ても、どこが面白かったかは、人によって全然違うように、アリの行動を2時間収めたビデオを見ても、人によってどこにフォーカスするかは、その人の個性になってきます。その切り口によって研究の取り組み方や論文の書き方も全然違ってくる。そういう意味では、自分は観察するのが好きだし、いろんな角度から考えることが好きだなと思います。
■アリの孤立と人間の孤独とは絶対的に違う
――本書のタイトルを見て、手に取ってみようと思う人が多いのは、人間の現代社会を反映しているように感じるからかもしれません。
古藤:そうですね。ただやはり孤立と孤独という言葉は、絶対的に違うんです。コロナ禍を経て、社会性のある生物にとって「交流」は必要不可欠であり、それがなくなると問題が生じるということは、広く認知されたと思います。でも私は「孤独」という言葉をアリに対しては使えません。「ぼっちのアリ」は物理的な孤立ですが、孤独を感じているかどうかはアリに聞いてみないと分かりません。
――でも、アリもストレスを感じているらしいことは、本書からも分かります。
古藤:はい。なので、孤立という枠のなかで生物として共通の応答があるのか、共通の遺伝子があるのかというところの研究は面白いところです。アリの実験、観察によって、分かることが絶対にあると思っていますし、いずれは非常に有効なモデルになるという直感は、10年前に出会った頃からありました。
――生物学全体の流れとして、かつては生物において最も重要視されていたのは脳だったのが、近年はそれだけではないという動きになっている気がしますが、本書を拝読していても、その流れが伝わってきます。
古藤:重要なのは脳だけじゃなかった、というのは確かに今のトレンドです。特に腸内細菌や腸の活動が生命活動に直結していることは、いろんな生物においても言われています。私もアリが社会的に孤立して死ぬ場合に、頭だけじゃなく腸も関係するんじゃないかなというところは当然注目していたんですけど、私の研究においては、また別の器官である脂肪体(多くの昆虫がもつ、哺乳動物における肝臓と脂肪組織の機能を併せ持つ組織)が、短寿命の鍵になっていることが分かっています。
詳しくはこの本を読んでいただければと思いますが、孤立アリは巣のなかに入らず、壁際で長くウロウロする傾向があります。より長く壁際の近くで過ごす孤立アリほど脂肪体の活性酸素量が増加している、つまり酸化ストレスが増悪していることがわかりました。このように遺伝子や分子などのレベルまで分析すると、人がストレスを感じたときに各器官がどうなっているのかと比較することで、人の研究にもフィードバックすることができる可能性があります。
■分からないことだらけだけど、だからこそワクワクする
――ところでアリはほとんどがメスですが、オスの存在も気になります。
古藤:オスの存在も面白いんですよ。ハチもそうなんですけど、結構かわいそうなんですよね。必要な存在であることは間違いなくて、研究室で飼っていてもたまに生まれるんですけど、集団ではあまり役に立っている感じではなくて、みんなに邪険にされているように見えるんです。
――メスだけで種を繋いでいけるのではないかと言われた生物もいましたよね?
古藤:完全に自分と同じクローンを作るアリというのも実はいるんですよ。
――そうなんですか。
古藤:ただそうやって近親交配であったり、クローンを作っていくと、遺伝的な多様性が失われます。するとたとえば何か伝染病のアタックにあったとき、全員が死滅してしまう可能性があり、種を繋いでいく法則とは全く逆のことが起きてしまいます。ですからアリにおいては完全にオスがいらないといったことは起こる可能性が低いのではないかなと。次の世代でオスとメスの新しい遺伝型を持った子孫が生まれるということは、彼らの社会にとって絶対に必要な仕組みだと思います。なのでちょっと切ない存在にも感じるオスですが、その命は繋がれていくというか、なくなることはないんじゃないかなと思います。
――それから知らなかったのですが、女王アリは一度の交尾で体に取り込んだ精子を、少しずつ何十年にも渡って使っていくのですか?
古藤:精子を蓄えるための貯蓄袋のようなものが体の中に備わっていると言われています。そこに精子がたくさん詰まっていて、そこから少しずつ少しずつ、受精させて産卵していきます。
――すごすぎます。体内における精子凍結保存のようなイメージでしょうか。
古藤:常温で何十年も。不思議ですよね。
――アリの集団でいうと、2割は何もしていないアリが必ずいるとも聞きます。その2割も必要なんだと。
古藤:働いていない個体がいるというのは、他の機関の研究で発表されていますね。ただ私たちの研究ではよく分かっていません。というのも子育てしている個体の中ではほとんど動かないこともあるようなんです。幼虫の上に覆いかぶさって幼虫を守っている個体がほとんど動いていない場合も、働いていないわけではないですよね。だからよく分からないんです。
――言われてみると「働いていないように見える」だけの可能性もありますね。
古藤:そうですね。仕事の定義はもっと細分化されているのかもしれませんし、何も意味を持たなさそうな行動がアリの社会では意味をもつのかもしれません。私たちが外で見ているものや、目で見ているものとは違う景色が、ここにはあるのだと思います。
――改めて、研究の題材に「アリの社会性」を選んでよかったと感じていることを教えてください。
古藤:一番面白いなと思うのは、決まったルートがないことです。私は、虫は興味どころか、むしろ好きじゃありませんでした。そんな私にとっても、知れば知るほど、アリは宝箱みたいな生き物。最初に二次元バーコードによる行動解析のお話をしましたが、アリの全部の遺伝子の発現量を調べるなんて技術は、私が留学した時代にやっと普及し始めたような段階でした。できたとしてもお金もものすごくかかる。それがこの10年で大きな変化が起きていて、より簡便に一つ一つの遺伝子を一網打尽に調べ、細胞の中で起きていることを覗きこめるようになりました。まだまだ分からないことだらけですが、だからこそワクワクする。その一例としても、本書に興味を持っていただけたらいいなと思っています。
(望月ふみ)