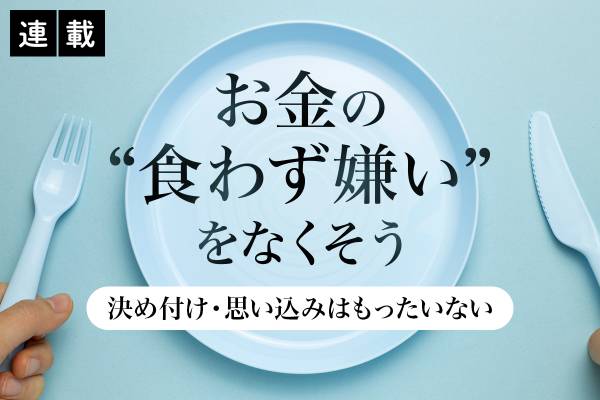連載 お金の“食わず嫌い”をなくそう──決め付け・思い込みはもったいない
「お金の話はするものじゃない」「稼ぎたい、儲けたいなんて下品」──。そう思っている人は多いでしょう。とかく「お金の話」はタブーと思われがちです。しかし、経済が自然と成長し、預金がいつの間にか増えるような時代は終わりました。お金の話は避けて通れません。お金に関する思い込みや、挑戦しないままにしている食わず嫌いを止めるには、「お金」と正面から向き合い、自分なりの付き合い方を見つけることが大切です。
第1回 「お金の話」は恥ずかしい?タブーの文化に変化の兆し
友人と貯金や投資について話したことはありますか?「そんなのあるわけない」と思われた方、なぜそう思われたのでしょうか。
なぜかお金の話をすると、「人間性を疑われる」「意地汚い人間だと思われる」といった意識が働くようです。
夫婦間でもお金の話をしない?
貯金や給料の額はたしかにプライベートな情報で話したくないかもしれませんが、「どんな投資をしているか」「毎月何割くらい貯めているか」といった話すら避けている人が多いようです。さらに、友人はおろか家庭内、夫婦間でもお金の話をしないこともあるようです(「へそくり」はその象徴とはいえないでしょうか)。
日本は「横並び意識の強い国」といわれています。そのため、お金があるにしろないにしろ、「周りには知られたくない」と思う傾向があります。実際にはお金がある家でも、お金がないかのように振る舞うケースもあります。
共働きする夫婦が増えていますが、以前は一人が働き、もう一人は家事をするという夫婦が多くいました。そうすると、お金を稼ぐほうとやりくりするほうで役割分担することも多く、「稼ぎに不満を言っている」「やりくりの仕方に口を出していると思われないか」という不安が、お金の話題を出しにくくさせたのかもしれません。
それでも、お金の話題を避けているからといって、本心から「お金が嫌い」という人は多くはないはず。お金があれば、人生の選択肢が増えます。「とにかくお金を稼ぎたい」「お金、お金」とガツガツする必要はありませんが、自分の人生を充実したものにするために必要なお金をしっかりと稼ぐことは大切です。
その上でお金の話題を避けることは、専門家に相談したり様々な情報を得たりすることから自分を遠ざけることになります。そうした姿勢は資産形成の足を引っ張りかねません。
「お金の話=恥ずかしい」という根拠のないタブーの文化に縛られ、お金の話題を避けるのはもったいないことです。
海外には「お金の授業」がある国も?
欧米諸国では、学校のカリキュラムでお金について学ぶ機会が設けられているケースも少なくありません。たとえばイギリスでは、3歳から金融教育がスタートします。年齢別の学習内容は次の通りです。
3~5歳
・お金の使い方
・お金を安全に保つ
・お金に関わる情報
5~7歳(日本の年中〜小学1年生)
・お金の記録の重要性
・お金を無くしたり盗られたりしたら
・貯蓄とその効果
・お金をどこから得るのか
7~9歳(同じく小1~小3)
・現金のみが支払でないこと
・簡単なお金の記録と予算
・人々の消費と貯蓄
・お金の貸し借り
・チャリティの役割
9~11歳(小3~小5)
・信用と負債
・簡単な家計管理
・インターネット詐欺の対策
・保険による保障
・学習と仕事・将来の経済的豊かさとの関係
・退職後の必要なお金
(北海道教育大学「イギリスにおける金融教育」より一部抜粋)
小学校低学年でお金の貸し借りや、現金以外の支払手段について学び、小学校卒業前に保険や退職後の生活資金について学ぶようです。こうした教育の機会がない日本からすると、かなり踏み込んだカリキュラムに映ります。
海外にはイギリスに限らずこのような教育を子どものうちから受けさせる国・地域があり、自然とお金について話すことがタブーでなくなり、マネーリテラシーが養われていくようです。
「お金の話」が当たり前になる時代
上で紹介したような授業は、日本では、どの学校でも行われているわけではありません。しかし、金融教育の遅れを取り戻そうという動きもあります。
日本銀行内に事務局を置く金融広報中央委員会が2005年から全国の幼稚園や小中高校などで「金融教育公開授業」を行っています。公開授業なので、教育関係者や児童・生徒らだけでなく、保護者、地域住民など誰でも参観できます。
2020年度は、全国10の学校で開催されました。授業では、「生活設計・家計管理」「金融や経済の仕組み」「消費生活・金融トラブル防止」「キャリア教育」などの分野を幅広く学ぶそうです。
また、少しずつですが「お金の話」を積極的にする人も増えつつあります。
結婚を機に、家計管理や資産形成について話し合ったり、夫婦で定期的にマネー会議を行ったり。子どもに家庭でマネー教育をしたり、SNSで家計簿や資産形成の状況を発信したり。友人同士で投資の情報交換をしたり。さまざまな形で行動し始めている人もたくさんいます。
このような変化の兆しは、政府が資産形成を後押ししていることと、一人ひとりの意識改革が進んできたことに起因していると考えられます。私たちのお金との向き合い方が、これからの日本のマネーリテラシー向上へとつながっていくことでしょう。
お金のある生活に憧れながら、自分には縁遠い世界だとあきらめる。お金のある富裕層をうらやみ、嫉妬する。質素倹約が美徳と自分自身に言い聞かせ、自らお金持ちになる道を閉ざしてしまう――。こんな行いを繰り返していては、いつまでも幸福は訪れません。
これからの時代、「お金の話」は決して恥ずべき話題ではありません。友人同士で、夫婦で、親子で、お金の話をすることが当たり前になっていくはずです。
自分や家族の将来の選択肢を広げ、人生を楽しむためにも、お金の話を少しずつ身近なものにしていきましょう。
文・木崎涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・濱田 優(dメニューマネー編集長)
【関連記事】(外部サイトに飛びます)
・初心者向け!ネット証券オススメランキング
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?
・つみたてNISA 毎月いくら積み立てるのがいい?