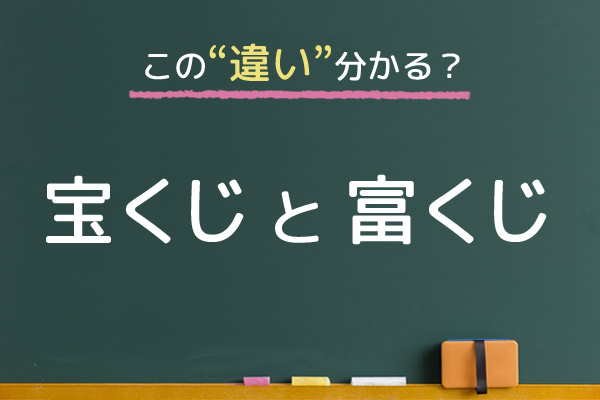一攫千金の代名詞である「宝くじ」や「富くじ」。大型の当せん金が狙える「ジャンボ宝くじ」は、年末ジャンボ以外にも「バレンタインジャンボ」や「ハロウィンジャンボ」などがあり、実は年に5回も発売されています。
「富くじ」も庶民の夢を託すものですが、「宝くじ」とは微妙に異なります。宝くじと富くじ、どう違うか分かりますか?
「宝くじ」と「富くじ」の歴史は長い
誰もが知る宝くじを改めて定義すると、「宝くじ」とは自治体の財政資金を調達するための当せん金付くじのことです。宝くじは売上金のうち約6割が当せん金と販売手数料で、残り約4割が公共事業に使われます。
宝くじの前身は、政府が軍事資金を調達するための「勝札」という名の抽せん券でした。ところが抽せん日前に終戦となってしまい「負札」などと揶揄されました。その後、戦災の復興資金を調達するために「宝くじ」として発売されたのです。
宝くじを発売できるのは「当せん金付き証票法」で定める全国都道府県と20の政令指定都市だけです。自治体は販売や事務などを金融機関に委託することができるとされています。一般の会社や個人が販売することは刑法によって禁じられています。
「富くじ」とは、江戸時代に寺社が主催した当せん金付くじのことです。現代の宝くじと同じく一般人が発売することは禁じられましたが、寺社だけは修復費用を調達するために発売が許されました。
結局は政府公認の富くじも江戸時代末期に禁止されてしまい、「勝札」が登場するまで富くじは発売されませんでした。
解答:「宝くじと富くじ」の違いとは……
宝くじとは、公共事業資金を調達するために地方自治体が発売する当せん金付くじのことで、富くじとは、かつて寺社が復興資金を調達するために発売した当せん金付くじのことです。
令和4年2月2日から3月4日まで販売しているジャンボ宝くじは、「バレンタインジャンボ」「バレンタインジャンボミニ」の2種類です。抽せんは3月11日に行われます。
文/編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・4月に変更!「年金を多く受け取る」ために知りたい3つのこと
・初心者向け!ネット証券オススメランキング(外部サイト)
・エスパー伊東さん「老人ホーム」に 入居費用は年金で足りる?
・株主優待をタダ取りする裏ワザとは?(外部サイト)
・ ガソリン代170円突破!節約のための2つのコツ
(2022年2月21日公開記事)